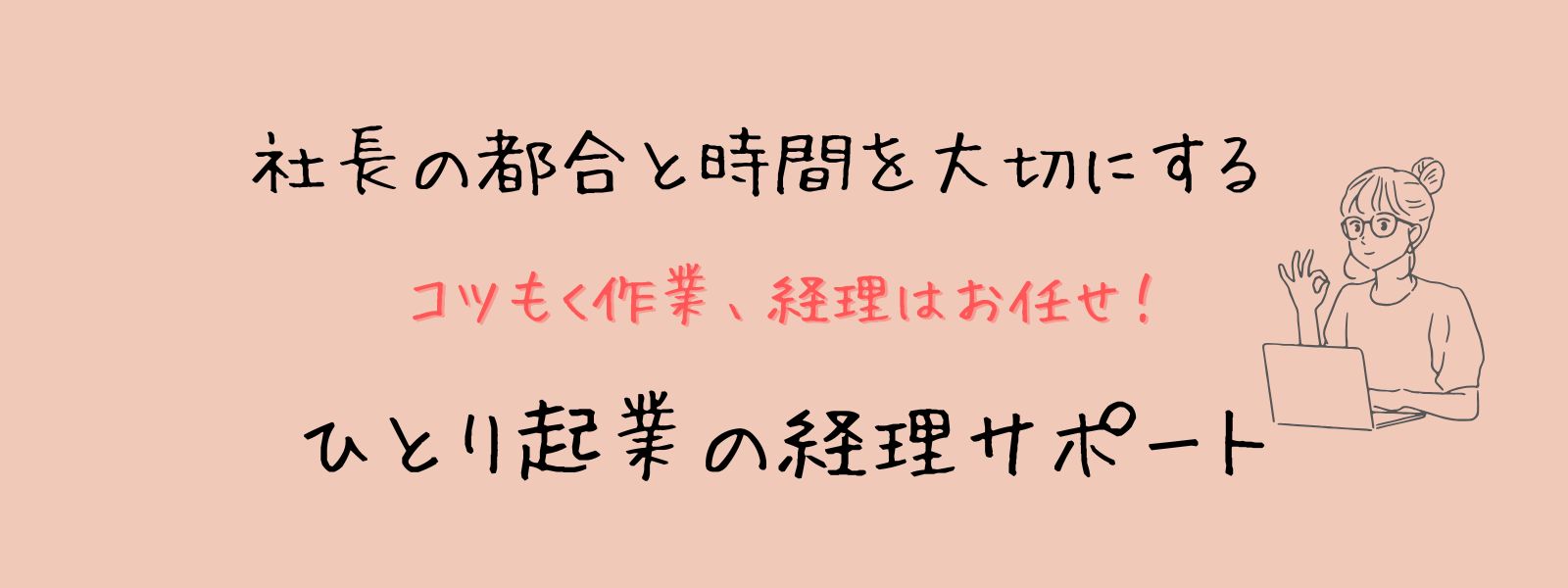確定申告をする場合には、スマホを使う、使わないにかかわらず、申告書にマイナンバーを記入するのが一般的です。
もしスマホでマイナポータル連携をすれば、マイナポータルからマイナンバーを読み取るので、申告書には自動的にマイナンバーが入力されるようになります。
またマイナポータルを使う場合には、様々な控除データなどをそのままマイナポータルから引っ張れるので、この点もマイナポータルを使うメリットになります。
ではマイナポータルを使う場合にはどのようにすればよいでしょうか?
マイナポータルを使う場合の事前設定
マイナポータル連携を利用する場合には、あらかじめマイナンバーカードを取得し、マイナポータルを事前に設定する必要があります。
国税庁のホームページから、確定申告書等作成コーナーに行くまではどのやり方でも共通です。
そこからマイナンバーカードを持っている人は、スマートフォンを使ってe-taxにするか、申告書を作成し印刷するかのどちらかを選ぶことになります。
ここでスマートフォンを使ってe-taxを選択し進むと、「マイナポータルと連携する」の画面が出てくるのでこれを選びます。
そしてマイナポータルと連携するには、マイナポータルの事前設定が必要になるのでこれを先に行う必要があります。
マイナポータルとは
まず、マイナポータル連携とはどういうことでしょうか?
税務署の説明によると、マイナポータル連携とはこのようなことを言います。
マイナポータル連携とは、年末調整手続きや所得税確定申告手続きについて、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
(税務署作成、令和4年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアルより引用)
そして、このマイナポータル連携を利用することによって、次の項で述べるようなデータの自動入力ができるようになったり、書類の保管や管理が不要になるなどのメリットがあります。
更にはマイナポータル連携をする時の事前設定は、最初の1回のみですので、次回以降の入力の手間が省けます。
このようにメリットが多いマイナポータル連携ですが、注意点があります。
それはスマホでのマイナンバーカードの読み取りに際してです。これは、お使いのスマホの機種によって細かく読み取り設定が決められていて、その通りに行わないとデータを読み込めないことがあります。
ここでつまづくと先に進めませんので、ここは丁寧に行うことをお勧めします。
マイナポータル連携でデータを自動入力する
ところで先ほどもマイナポータル連携のメリットでお話ししましたが、連携することにより自動取り込みできるデータとしては、次のようなものがあります。
〇医療費
〇ふるさと納税
〇公的年金などの源泉徴収票
〇国民年金保険料
〇住宅ローン控除
〇生命保険、など
申告書作成でカメラを利用する
それから申告書を作成する場合、スマートフォンのカメラから資料を作成し、それを自動的にデータとして読み込む機能があります。
実際に国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から医療費控除を入力する画面に進んだ場合、カメラで源泉徴収票を撮影し、それをデータに読みこむと、所得金額、所得控除の額、税額、還付額などが自動的に入力されるようになります。
ですから、カメラ機能を使うことによって、自分で入力する手間も省けますし、計算間違いを防ぐこともできます。
このようにスマートフォンで申告をした場合、かなりの手間が省けるのは助かりますね。
スマートフォンでマイナポータル連携で確定申告の作成と申告が一度におこなうことができます。
これは本当に楽ですね。